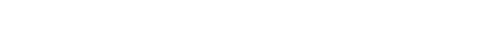令和7年度の労働・社会保険関係法令の改正について
2025年4月1日
【育児・介護休業法関係】
■子の看護休暇の見直し(子の看護等休暇)
対象となる子の範囲を「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校第3学年修了まで」に拡大し、取得理由についても新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式を追加。また、労使協定により除外できる労働者から「継続雇用期間6ヵ月未満」を撤廃する。こうした改正に伴い、名称は「子の看護等休暇」とする。
■所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求が可能となる労働者の範囲を「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大する。
■育児休業等の取得状況公表義務の適用拡大
男性の育児休業等の取得状況の公表義務の対象を「常時雇用する労働者数1,001人以上」の企業から「同301人以上」の企業に拡大する。
■育児・介護のためのテレワーク(努力義務)
3歳に満たない子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者がテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが事業主の努力義務とされる。
■短時間勤務制度の代替措置の選択肢拡大
3歳に満たない子を養育する労働者に、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークを追加する。
■介護離職防止のための個別の周知・意向確認
家族の介護の必要性に直面した旨の申出をした労働者に対し、事業主が介護両立支援制度等に関する情報(制度の内容)を個別に周知し、当該労働者の制度利用に関する意向を確認することを義務付ける。
■介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
「労働者が40歳に達する日の属する年度」または「労働者が40歳に達した日の翌日から1年間」のいずれかにおいて、労働者に対し介護両立支援制度等に関する情報提供を行うことを事業主に義務付ける。
■介護離職防止のための雇用環境整備
介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の①~④のいずれかの雇用環境整備の措置を講じなければならないこととした。
●雇用環境整備の措置
①介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
■介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定により除外できる労働者から「継続雇用期間6ヵ月未満」を撤廃する。
■「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し
育児・介護休業法に定める介護両立支援制度等の対象となる家族については年齢に制限は設けておらず、厚生労働省が定める「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に当てはまれば、介護両立支援制度等を利用することができる。 他方で、現在の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」では、例えば子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースもあるとの指摘があり、これらを踏まえ、今般の介護両立支援制度等の強化に併せて見直しを行った。
【雇用保険法関係】
■雇用保険料率の見直し
雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で〔一般の事業〕14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)、〔農林水産等事業〕16.5/1,000(労働者負担:6.5/1,000、事業主負担:10/1,000)、〔建設の事業〕17.5/1,000(労働者負担:6.5/1,000、事業主負担:11/1,000)とする。
■雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
○自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮する。
〇自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる。
■高年齢雇用継続給付の支給率の変更
支給率を最大15%から10%に変更する。
■出生後休業支援給付金の創設
子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業等を取得した被保険者に対し、育児休業給付等に上乗せして支給する給付金を創設。
■育児時短就業給付金の創設
2歳未満の子を養育する被保険者が育児のために時短就業をした場合に、時短就業中に支払われた賃金の最大10%を支給する給付金を創設。
■育児休業給付金の延長申請の要件厳格化
育児休業給付の支給対象となる育児休業の延長(1歳以降)について、保育所等に入れなかったことを理由とする延長事由の要件を厳格化。速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限るものとする。
■出生時育児休業給付金の支給申請期間見直し
出生時育児休業給付金の対象となる出生時育児休業(産後パパ育休)が、子の出生日等から8週間を経過するまでに終了した場合(28日取得または2回目が終了)に、休業を終了した日の翌日から申請可能とする。
【高年齢雇用安定法関係】
■高年齢雇用確保措置の経過措置の終了
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められた経過措置が終了。
【職業安定法関係】
■紹介手数料に関する情報開示
職業紹介事業者に求める紹介手数料に関する情報開示事項に、職種ごとの平均手数料率の実績を追加する。
【障害者雇用促進法関係】
■除外率の引き下げ
障害者の就業が困難であると認められる業種に対する除外率を一律10ポイント引き下げる。
以上、主なものを抜粋(月間社労士2025.3より)